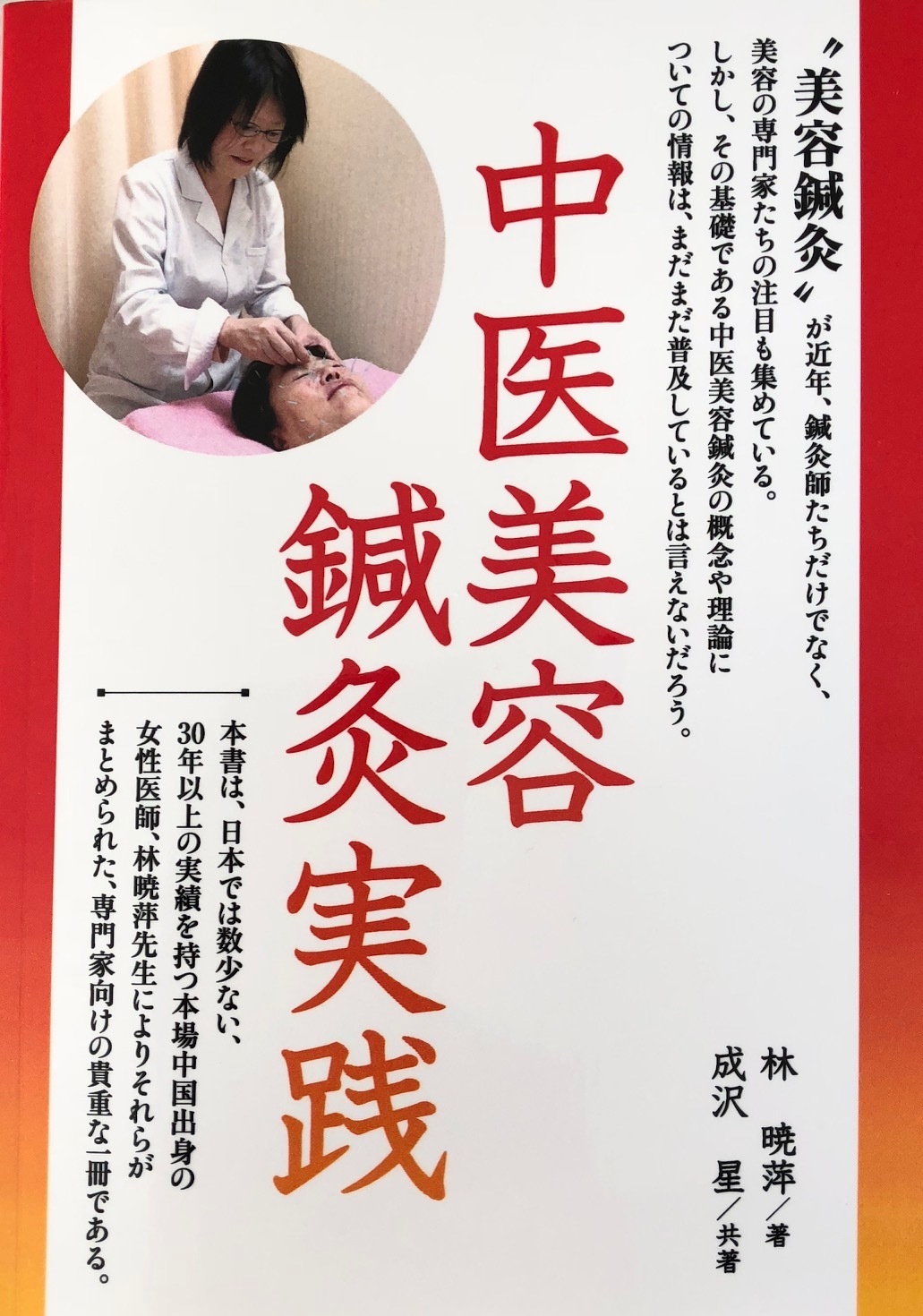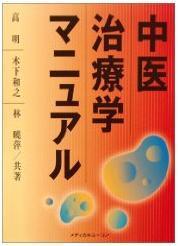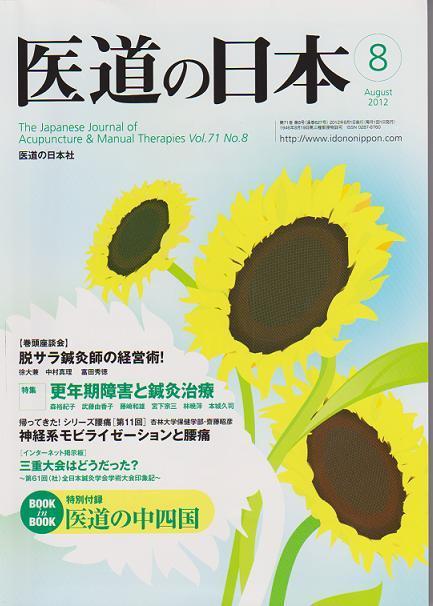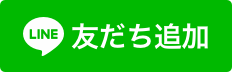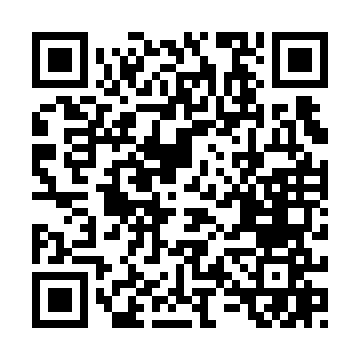40年の経験、実績と信頼!東京・三鷹にある難病など様々の症状に対応する中国鍼灸の林鍼灸院にお任せ下さい(日本語・中国語・Englishに対応)
気・血・精・津液について
気・血・精・津液とは
東洋医学では気・血・精・津液とは人体を構成する基本的な物質で、それぞれ人体におけるはたらきは異なります。これらが充実し円滑に巡ることによって、組織・器官などの人体における各種の生理活動が機能し、生命活動が維持されます。
これらのうちどれかが不足したり滞れば、人体ではバランスが崩れて不調を起こします。そのため、これらの生理的機能を知ることは東洋医学的な病態把握のために欠かせないもので、東洋医学による診断・治療を行うための基礎となります。
また、これらも「陰」と「陽」に二分することができ、物質性が低く運動性が高いものを陽、物質性が高く運動性の低いものを陰とし、気は陽の部分、精・血・津液は陰の部分と考えます。
気
気とは、形としては見えないもので、生命エネルギーそのものを指します。人体においては血液の流れをよくしたり、人体の組織・器官を正常に働かせたりする、生命活動のエネルギー源です。
(気の生成)
飲食物が脾や胃のはたらきによって消化吸収されてできた水穀の精微、肺の呼吸により得られる自然界の清気、先天の気である腎の精気から生成されます。
(気のはたらき)
①推動作用
気は人体を休むことなく巡り、人体の成長・発育や、組織・器官の働きを促進して正常な生理機能を発揮させます。他に精・血・津液を押し動かし人体に巡らせる働きもあります。
②温煦作用
気には人体の組織・器官を温める作用があり、これにより体温を一定に保ち正常な生理機能を発揮させます。
③固摂作用
気は精・血・津液の過度なに流失するのを防ぎ、正常な分泌や排泄などを維持します。
④防衛作用
気は体表を覆い、外からの邪気が人体に侵襲するのを防いでいます。また体内に侵襲した外邪に対抗する役割を担います。
⑤気化作用
物質を転化させる作用のことで、気の生成や精・血・津液への転化、排泄物の生成など物質の各種の変化はこの作用によって起ります。
血
血とは、狭い意味では血液のことをいいますが、広い意味では、からだに栄養を与える物質のことを指します。気の推動作用を受けて人体を巡り、全身をくまなく滋養します。また精神活動を安定させるはたらきもあります。血が充実していれば五臓六腑が担っているはたらきが円滑に機能し、心身ともに健康で安定した状態となります。
(血の化生)
飲食物が脾や胃のはたらきによって消化吸収されてできた水穀の精微や、先天の気である腎の精気から化生されます。
(血のはたらき)
①滋養
血には人体に必要な栄養物質が豊富に含まれていて、気の推動作用によって全身を巡り組織・器官をくまなく滋養することで、これらは正常な生理機能を発揮します。このはたらきが正常に行われているかどうかは、顔色・皮膚・毛髪・筋肉・感覚・運動などに反映されます。
②神の維持
神とは、生命活動の総称のことを指しますが、ここでは特に精神活動のことを言い、血によってその機能は正常に維持されます。血の滋養が不足すると精神活動に失調が現れやすくなります。
精
精とは、人体の構成や生命活動を維持するのに最も基本となる物質で、組織・器官を滋養したり、気・血といった他の生理物質を化生(変化・生成)します。生殖能力を持つ生殖の精を指すこともあります。
(精の化生)
精は、父母から受け継いだ先天の精と、飲食物の摂取によって得られた後天の精の補給によって維持されます。先天の精は成長や発育の源となり、後天の精の一部は気・血に化生され全身の組織・器官に行きわたり、残りの一部は腎に貯えられます。
(精のはたらき)
①生殖
精には生殖機能の成熟を促すはたらきがあります。
②滋養
精には人体の組織・器官を滋養するはたらきがあり、これが充足していれば人体における各種の生理機能は正常に発揮されます。
③気・血への化生
精は必要に応じて気や血といった他の生理物質に変化します。精が充足していれば、気・血は正常にはたらきます。したがって、精は生命の本源であり、人体を構成する最も基本的な物質と言えます。
津液
津液とは、体内における血以外の水分のことを指し、その充実によって人体は潤いや柔軟性を与えられます。
(津液の化生)
飲食物中の水分が脾や胃のはたらきによって吸収されて津液となります。生成された津液は肺へと運ばれ、三焦(さんしょう)という通路を通って全身に散布されます。
(津液のはたらき)
全身に散布された津液は、体表の皮毛や肌肉を潤し、体内の臓腑を滋養します。また関節に入れば、関節の動きを滑らかにするなどし、人体に柔軟性を与えます。
(津液の代謝)
津液の代謝とは、津液の生成・輸布(全身に輸送・散布すること)・排泄の過程を言い、多くの臓腑のはたらきによって行われています。
主に、津液の生成には脾、輸布には肺、排泄には腎が、重要な役割を担っています。
生理物質の病理的変化
これらの生理物質のうちどれかが不足したり滞れば、人体ではバランスが崩れて不調を起こします。生理物質の病態は虚証(不足や機能減退)と実証(有余や停滞)に大別され、気の病理的変化では気の不足(気虚)と気の滞り(気滞)、血の病理的変化では血の不足(血虚)と血の滞り(血)、津液の病理的変化では津液の不足と津液の停滞(痰湿)が主に見られます。
東洋医学の治療においては、これらの病態を把握することはとても重要です。詳しくは気血津液弁証のページでお話します。
ホームページのQRコード