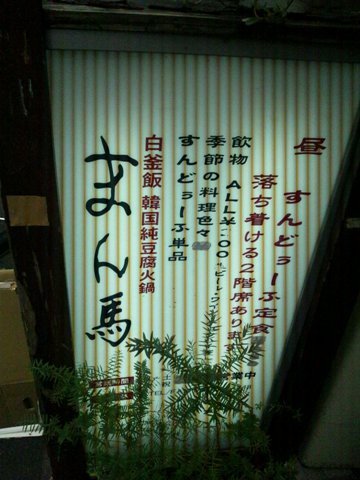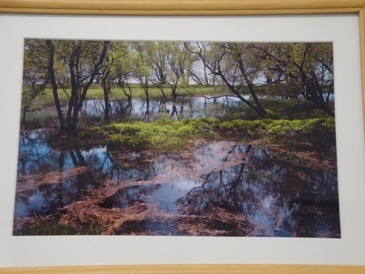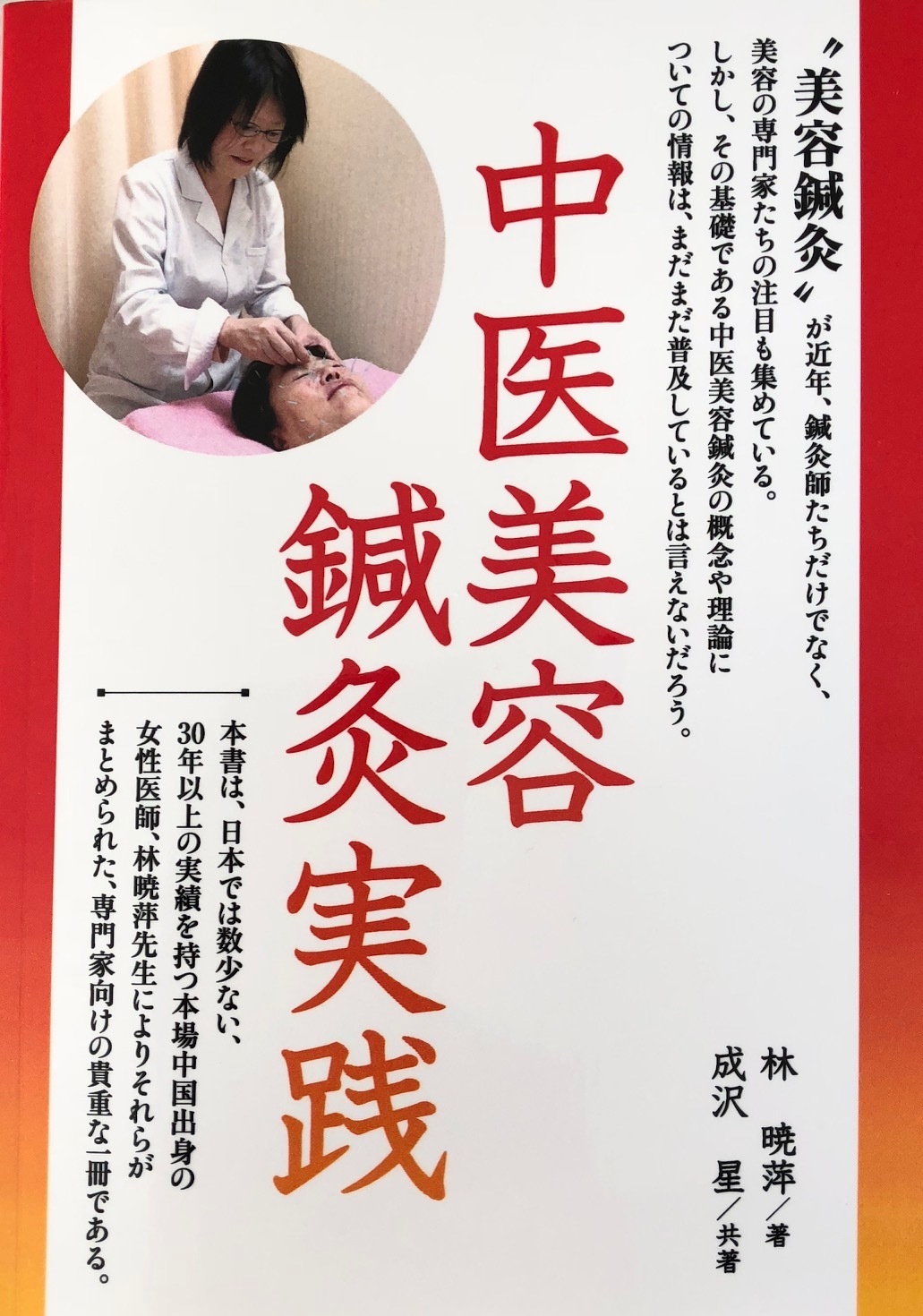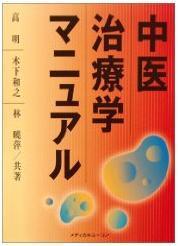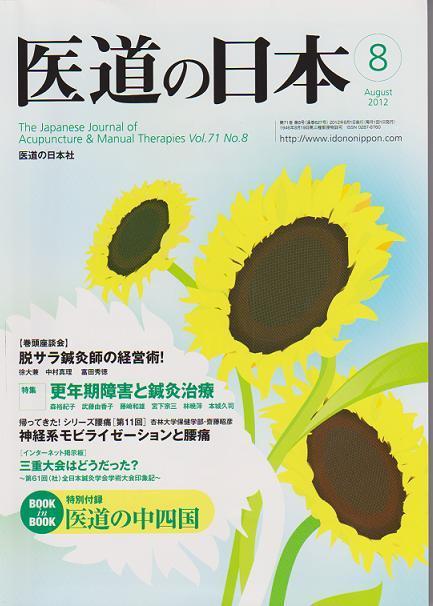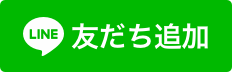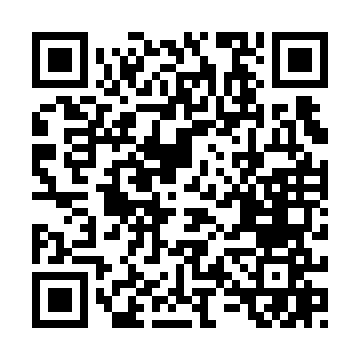40年の経験、実績と信頼!東京・三鷹にある難病など様々の症状に対応する中国鍼灸の林鍼灸院にお任せ下さい(日本語・中国語・Englishに対応)
2014年1月14日
早くも1月の半分を過ぎました。皆さんがお正月の長い休みで十分充電しましたよね。
皆様にご報告したいことがありまして、当院では新しい年にスタッフも入り替えました。
皆様になじみした南野先生が当院から卒業しまして、これから自分の開業を向かって頑張っていくことになりました。とても優しい、パリパリでお仕事をしていただきました先生で、当院にとってとても残念でしたが、本人の為にも頑張ってもらいたい気持ちもありましたので、どうか、南野先生のご活躍をお祈りします。
また、新しい入った平井先生が関西医療大学を卒業した若い先生です。
これからも、宜しくお願い致します。
2014年1月20日
西梅田から歩いて3分ほどの場所に小さな韓国料理の店を発見!
しかもスンドゥブ料理の専門店で、ランチは女子の行列ができるほどの人気店です。
「まん馬」と書いて「まんま」の読むのでしょうか・・・
店自体は小さくて、一瞬戸惑います(笑)が、2階があるんですね〜
でも2階も狭いです^^;
2014年1月24日
2014年1月28日
2014年2月4日
2014年2月11日
近年、「首の痛み」のある人がかなり増えてきました。
「首の痛み」とは、肩甲骨周辺から後頭部の辺りまでを含めた痛みを指し、多くの人が日常的にこの痛みを経験しています。
そのほとんどは、筋肉の疲労などによるもので、心配はいらないが、パソコンやスマホ等のやり過ぎ、目の疲れなど首の痛みの原因となる要素を挙げている。
一般に、首の痛みの約9割は原因がはっきりしていません。多くが筋肉の疲労や精神的なストレスが関係しているとされ、鍼などの治療により、1、2週間で改善することが多く、あまり心配しなくてもよいものです。
しかし、残りの約1割は明らかな原因があるもので、原因として、
1.骨に転移したがん
2.感染症(細菌の感染で起きる化膿(かのう)性脊髄炎)などの病気
3.骨折・脱臼といった外傷
4.「頚椎椎間板ヘルニア」「頚椎症」「後縦靱帯骨化症」などがあげられます。
これらは専門的な治療が必要となるため、痛みが長引くようであれば原因を調べ、原因に応じて適切な治療を受けることが大切です。
2014年2月18日
1月末と2月初めに顔面神経麻痺の患者様の4人の女性が当院に来られました。そのうち3人が発症1週間以内、1人が1か月以内に当院の鍼灸治療を受けました。4人とも早いスピートで回復しました。本人たちがとても喜んでくれました。やはり、早いうちに鍼灸治療を受けて良かったと思います。
冬と春先に顔面神経麻痺にかかりやすい季節なので、元々冷え症を持つ方、特に注意する必要があります。
ストレスが溜まらないよう、十分な睡眠をとって、身体を冷やさないような対策を心かけましょう!
2014年2月25日
休日にお久しぶりに肉まんを作りました。
生地から手作りなので、中身が白菜と豚肉で、汁を出てきて、とても美味しかたです。
私流な作り方ですが、ご紹介したいとおもいます。
①ブロック豚肉を細かく切る。
②白菜も細かく切る。
③細かい肉を少し水を入れて混ぜる、サラダ油、ごま油、塩コショウを入れて混ぜた後、ねぎ、生姜を入れてまた混ぜる。最後に細かくした白菜を入れて混ぜる。
④予め発酵した生地を皮を作って中身を包む。
⑤鍋で20分で蒸し。
⑥出来あがった肉まんを醤油やお酢やごま油等作ったたれで、召し上がる。
興味を持っている方がぜひ作ってみてくださいねお勧めです
2014年3月7日
当院に通った3人の方から赤ちゃん誕生の連絡がありました。
本当におめでとうございました!
当院の鍼灸治療により、長年悩まれた不妊症が完治し、妊娠出来る事は、とてもうれしかったです。
これからも東洋医学の良さと今までの臨症経験を生かし、もっともっと多くな不妊症および難病に悩まれた方を改善出来るように頑張りたいと思います。
3月11日(火)
日曜日に松山市にある愛媛県中医研究会に講師として招かれ、特別講演を行いました。
テーマは「不妊症に対する中医学的な治療法」でした。実演も行いました。
医師、鍼灸師、鍼灸学校の学生さんなど60名以上の方が参加し、とても熱心に講演を聞きました。そして、沢山の質問をしてきました。
初めて、四国に行って、飛行機の中から、下を見ると、たくさんの島があって、しかも、人が住んでいるのにびっくりしました。
日帰りで、疲れもありましたが、とても有意義で、楽しい一日でした
3月18日(火)
15日〜16日に「国際中医薬学術大会」が台北で開催されました。日本からの19名を含め外国からの参加者が260名、台湾からの参加者が1600前後で、とても大盛況の大会でした。
各国からの参加者から学術発表があって、特に“中国黒竜江中医研究院院長・中医鍼法学会理事長”ー張縉教授の「鍼刺手法治療運用と効果に関する」、“南京中医薬大学第一臨床医学院産婦人科教室”ー談勇教授の「卵巣機能低下の中医治療」の発表内容は私にとって非常に勉強になりました。
そのあと、台湾大学付属病院にも見学しに行きました。
ちなみに台湾呉副総統も大会に来られて祝辞を述べました。
2014年3月24日
2014年3月31日
先日、尼崎にある薬膳料理鉄板焼シネマで上谷先生の送別会を行いました。
上谷先生が当院に2年間務めていただいてとても真面目な先生でした。当院にとって残念の事ですが、不妊治療専門なクリニックの就職で、おめでたいことでした。
これからも西洋医学の先進治療を勉強しながら、一層鍼灸治療を取り組んで頂きたいですね。
ちなみに、国際中医薬膳師の女主人が作った薬膳料理を食べて体に良い物を味わえて薬膳にも興味がわいてきましたて、最高の食事でした。
2014年4月2日
寒い冬も終わり、いよいよ穏やかな陽気の春が到来。店先にも初物の野菜が並び始める頃です。毎日の食生活で欠かすことのできないのが「野菜・くだもの」。身近な存在でありながら、私たちはその大切さをあまり理解していないのかもしれません。
季節ごとに「旬」の野菜・くだものを食べる
◎野菜・くだものは身体にどのような働きをするのでしょうか。
食物には栄養の他に、身体の機能を整える役目もありますが、なかでも野菜・くだものはビタミンやミネラルが多く含まれていたり、豊富な食物繊維が腸内環境を整えるのにも役に立ち、腸内を健康にすることで体全体の免疫力アップに繋がります。
野菜・くだものの色や香りには、ポリフェノール、カロテイド、リモノイド、硫化アリルなど「フィトケミカル」と呼ばれる成分が含まれています。強力な抗酸化力や健康に良い作用があることがわかり、注目されていることから生活習慣病予防は、野菜・くだものを彩りよく食べることが大切です。
日本ではハウス栽培などで旬を問わず、野菜・くだものを購入することができますが、やはり春には春の、夏には夏の、「旬」の野菜・くだものを食べる事をおすすめします。旬のものは味わいが深く、栄養価が高く、値段も手頃になるので、身体に優しく家計にも優しいのです。
春に旬を迎える野菜は、フキノトウ、タラの芽、ウド、タケノコなど苦味や渋味を含んだ芽吹き野菜が多いのが特徴です。苦味や渋味の成分は老廃物を排出する働きがあると言われています。冬は過食や運動不足などで体重が増加する人も多く、脂肪を体に貯め込みやすい季節でもありますね。そんな冬に貯め込んだ体内の不要なものをデトックスしてくれるのが春野菜です。
◎おすすめの春の野菜・くだもの
○アスパラガス
アスパラガスは若芽なのですが、2〜3年もの期間をかけて根っこが大きくなるように育てられます。蓄積された栄養がギュッとつまったところで芽吹いた若芽が収穫されるので、とても栄養価の高い野菜です。
新陳代謝を活発にするアスパラギン酸や高血圧を予防するルチンも含まれています。
○春キャベツ
冬のキャベツに比べて、フワっとした巻きで葉は柔らかくみずみずしく、さわやかな甘みがあります。千切りキャベツやサラダなど生食が合います。
芽キャベツや結球しないタイプの芽キャベツ・プチベェールも春が旬。軽くソテーして食べるのがおすすめです。
2014年4月11日
桜花が散り、木の新芽が出始め、皆さんはお花見をしましたか?
当院には、先日、1人の方から、ご出産の報告、3人の方からがご懐妊のご報告を受けました。とてもうれしいと思ってます。おめでとうございます。
その中1人の方が38歳で、結婚4年目の初めてのご妊娠、もう一人の方が45歳で、体外受精で初めてのご妊娠です。皆さんが順調でいきますように!
また、詳しくご報告するから、ぜひ見てくださいね。
2014年4月20日 雲⇒晴れ
先週の休日に造幣局にお花見に行きました。
たくさんの種類で、とてもきれいな桜でした。屋台も沢山並び、とても楽しかった。
2014年5月7日
春めいてほわほわな毎日ですが、皆様GWいかがお過ごしですか。
当院では5月からスタッフが増えました
前に当院で働いた高橋先生は産休が終り、5月から復帰しました
もう一人の遠藤先生は研修が入りました
2人とも暫く土曜日だけ出ますので、どうぞ、宜しくお願い致します
2014年5月12日
GWに来日した姉と妹と6年ぶり日本で再会した
アメリカに住んでいる姉と中国に住んでいる妹と三姉妹の顔あわせがなかなか難しくて、今回の来日でとても嬉しかった
短期の滞在でしたが、仕事が終わって、家に帰ってきて、すぐご飯を食べられ、家事もやってくれました。とてもありがたくて、幸せでした。心より感謝してます
2014年5月20日
当院の蘭の花が今年も開花しました
この蘭は6年前、当院が開業するときに頂いたもので、6年間休むことなく毎年、綺麗に咲いてくれます
患者さんに「蘭の花は育てるのが難しい。毎年花をつけるのはすごい。」と教えて頂きました。
きちんとお世話できていたのでしょうか?お世話した分、咲いてくれてとてもうれしいです来年も咲いてくれるようがんばります
ホームページのQRコード